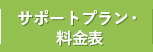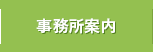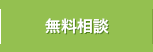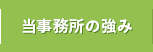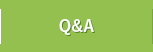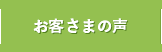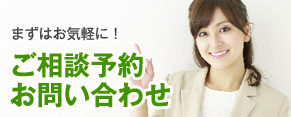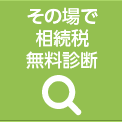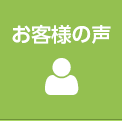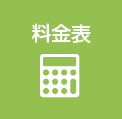相続税の「物納」新ルールを専門家が図解|可能性と“変わらない”現実
「相続税、現金で払えないかも…」そんな時、不動産で税金を納める「物納」は使えるのでしょうか?令和7年度の税制改正で、この物納制度の計算方法が見直され、特定の条件下では新たな選択肢となる可能性が出てきました。しかし、手続きが簡単になるわけではありません。この記事では、専門家の視点から、新制度で広がる可能性と、変わらない現実をわかりやすく解説します。
なぜ今、相続税のルールが見直されるのか?
「資産のほとんどが不動産で、納税用の現金がない」という相続が、高齢化社会で現実的な問題となっているからです。 日本の高齢化が進むにつれ、遺産といえば長年住んだ家やアパートが中心で、すぐに使える現金が少ない、というケースは珍しくありません。現行制度のままでは、納税のために大切な不動産を不利な条件で急いで売却せざるを得ない事態も起こり得ます。そこで国は、分割払いである延納(えんのう)や、不動産で納める物納(ぶつのう)の制度を、より実態に即したものへ見直すことを決めました。これは、納税者が追い詰められる前に、取りうる選択肢を社会として整備しようという重要な動きです。
「なぜルールが見直されるのか?」のポイント
高齢化により、資産の多くが不動産という相続が増加し、現金での納税が困難なケースが問題となっています。この実態に対応するため、国は最終手段である「延納」や「物納」の制度に一部、見直しを加えました。
【図解】なぜ『物納』の可能性が広がるのか?
新制度のポイントは、分割で払える額(延納額)をより現実的に計算することで、結果的に物納できる枠が広がる点にあります。 この計算の変化を、シンプルな図で見てみましょう。相続税の総額を「大きなコップ」だと考えてみてください。このコップを、まず「①手持ちの現金」で満たし、次に「②分割払い(延納)」で満たしていきます。そして、それでも満たしきれなかった「残りの空きスペース」が、不動産などで納める「③物納」の枠になります。
【従来の計算イメージ】 相続税の総額(コップ) +----------------------+ |③物納できる枠 |← この部分が小さい +----------------------+ | | | | |②分割払い(延納) |←「最長20年」等で計算され、非常に大きい | | | | +----------------------+ |①手持ちの現金 | +----------------------+ 【新しい計算イメージ】 相続税の総額(コップ) +-----------------------+ | | | | |③物納できる枠 |← ★この部分が広がる! | | | | +-----------------------+ |②分割払い(延納) |←「平均余命」等で計算され、縮小 +-----------------------+ |①手持ちの現金 | +-----------------------+
新しい制度では、②の分割払いの額を、その人の「平均余命」や「将来の収入減」を考慮して計算します。 これにより、分割で払える額がより現実的な大きさに縮小されます。その結果、コップに大きな空きスペースが生まれ、③の物納できる枠が広がる、という仕組みです。これにより、従来は対象外だった方でも、物納が選択肢として視野に入ってくるのです。
「物納の可能性が広がる仕組み」のポイント
新制度では、分割払いで納める額を平均余命などを考慮して現実的に計算します。その結果、分割で払いきれない「残りの部分」が大きくなり、不動産で納める「物納」の枠が広がる可能性が生まれます。
ご注意!手放しでは喜べない、依然として残るハードル
制度が見直されたとはいえ、物納の手続き自体が極めて複雑で、専門知識や多額の費用を要するという現実は何一つ変わっていません。 「物納の可能性が広がる」という事実は、あくまで入口の話です。実際に物納を申請するには、土地の境界を確定させたり、測量図を作成したりと、国がスムーズに財産を受け取れる状態に「整備」する責任と費用が申請者側に求められます。これらの準備には、専門家への報酬を含め数十万〜百万円以上の費用がかかることも珍しくなく、時間も数ヶ月単位で必要です。この巨大なハードルは依然として残っており、誰もが気軽に使える制度ではないことを強く認識しておく必要があります。
だからこそ、安易に「物納ありき」で話を進めるのは危険です。 当事務所では、この改正を「万策尽きた時の選択肢が、少しだけ改善された」と冷静に捉えています。物納は、あくまであらゆる手段を講じても納税資金を用意できない場合の最終手段の一つ。不動産を有利な条件で売却する、金融機関から融資を受けるなど、他の方法とも徹底的に比較検討することが不可欠です。「うちの場合は、この制度を使えるだろうか?」と少しでも気になったら、思い詰める前に、まずは私たち専門家にご相談ください。
「依然として残るハードル」のポイント
物納は、土地の測量や登記など、申請者負担の煩雑な手続きと多額の費用が伴うという現実は変わりません。安易に頼るのは危険であり、専門家と相談し、売却など他の選択肢と比較検討した上で慎重に判断することが重要です。
□■ この記事のまとめ ■□
令和7年度の税制改正で、相続税の物納が特定の条件下で選択肢になり得ます。特に不動産資産が多い高齢の方には可能性が広がりますが、手続きは依然として複雑で費用もかかります。利用を検討する際は、専門家への相談が不可欠です。
よくあるご質問(FAQ)
この改正はいつから適用されますか?
相続税については、令和7年(2025年)4月1日以後に発生した相続から適用されます。
どんな不動産でも物納できるわけではないのですか?
はい、その通りです。国が管理・処分しにくい不動産(境界が不明確、権利関係で争いがあるなど)は「管理処分不適格財産」とされ、物納に使うことは認められていません。この基準も依然として厳しいものがあります。
相談だけでも費用はかかりますか?
当事務所では、初回の簡易的なご相談は無料で承っております。物納という選択肢を考える前に打つべき手がないか、一緒に状況を整理しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
『物納』の判断に迷ったら専門家へご相談ください
相続税の「物納」は、今回の改正で可能性が広がったとはいえ、手続きが複雑で誰にでも最適な方法とは限りません。「自分のケースでは延納と物納、どちらが有利なのか?」「そもそも、この不動産は物納できるのだろうか?」など、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、名古屋相続税無料診断センターの無料相談をご利用ください。
相続税申告はもちろん、遺産分割や納税資金の準備まで、相続に関するあらゆるお悩みに、相談実績豊富な専門家が対応します。お客様に親身に寄り添い、円満な相続の実現をサポートすることをお約束します。初回60分の相談は無料です。まずはお一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
参考文献
関連ページ
著者情報
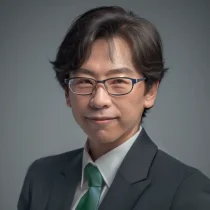
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
コラムの最新記事
- 相続税の税務調査は「実地調査」だけじゃない?増える“電話・手紙”と、無申告への厳しい視線【令和6事務年度】
- 引っ越しだけじゃない ペンリィが変えるかもしれない「死亡・相続手続き」のこれから
- 見つからない不動産"を防ぐには?2026年開始の新制度「所有不動産記録証明制度」の賢い使い方と知っておべき限界
- 『配偶者に全部』は本当に安心? 名古屋で考える二次相続モデルケースと対応策
- 兄弟で揉めない「実家の空き家」相続ガイド|後悔しないための3つのステップ
- 「私の場合は使える?」名古屋市の空き家3000万円控除、対象か3分で診断【税理士監修】
- 【名古屋市版】空き家相続の放置コストを1分で簡単シミュレーション!税金が6倍になる『特定空家』指定前に税理士が教える3つの対策