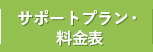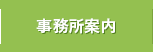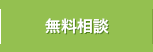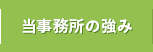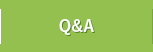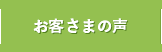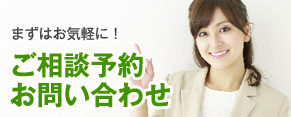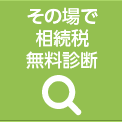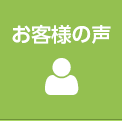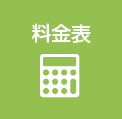兄弟で揉めない「実家の空き家」相続ガイド|後悔しないための3つのステップ
実家の空き家相続で兄弟と揉めたくない方へ。税理士の佐治英樹が解説します。
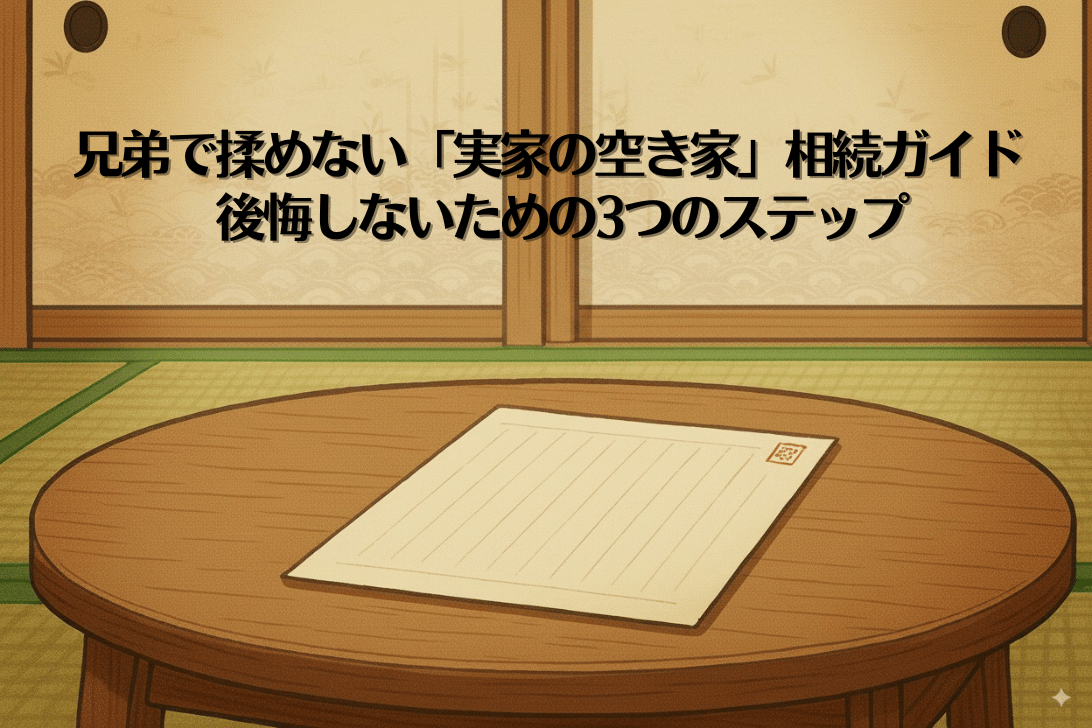
「親が元気なうちは、まだ先のこと…」そう思うお気持ちは、とてもよく分かります。しかし、国の最新調査によれば、日本の空き家の約6割は「相続」をきっかけに、ある日突然、向き合うべきテーマになります。特に、子どもたちがそれぞれ家庭を持ち、遠方で暮らしている場合、ご実家の管理や将来についての話し合いは、ご兄弟姉妹にとって非常にデリケートな問題となりがちです。
この記事は、そんな漠然とした不安を抱える方に向けて書きました。客観的なデータで「なぜ早めの準備が大切なのか」をご理解いただき、最も大切な家族の絆を守りながら前に進むための具体的な方法を、以下の3つの問いに答える形でお伝えします。
- なぜ実家の話は、兄弟にとって難しいテーマになるのか?
- 先延ばしにすると、どのような心配事が増えるのか?
- 家族で円満に解決するための具体的なステップとは?
なぜ「実家の空き家」は揉めごとの火種になるのか?最新調査が示す2つの現実
「ウチの兄弟は仲が良いから大丈夫」と思っていても、実家の話となると、なぜか少しギクシャクしてしまう。それには、多くのご家庭に共通する構造的な理由があります。国の最新調査からは、「心の準備ができていない」こと、そして「負担に偏りが生まれやすい」ことという2つの現実が浮かび上がってきました。
現実①:心の準備なく「突然」向き合うことになるから
国土交通省の最新調査によると、空き家を取得した経緯で最も多いのは「相続」で、実に57.9%にのぼります【出典:1】。これは、日本の空き家の半分以上が、ご家族の誰もが落ち着いて考える時間がないまま、大切な方を亡くされた直後に、現実的な課題として目の前に現れることを意味します。悲しみや思い出が交錯する中で、家の処分という大きな決断を迫られるため、冷静な話し合いが難しくなりがちなのです。
現実②:「誰かが…」という気持ちが、負担の偏りを生むから
ご兄弟がそれぞれ別の場所で暮らしている場合、問題はより繊細になります。同調査によれば、空き家所有者のうち、自宅から徒歩圏内に住んでいる方は約36%に過ぎません【出典:1】。多くの方は、管理のために時間と交通費をかけているのが実情です。結果として、ご実家近くに住む特定のご兄弟に負担が集中し、「自分ばかりが大変な思いをしている」という気持ちや、逆に「遠くにいるから任せきりで申し訳ない」といった、お互いの遠慮や不公平感が生まれやすくなります。この物理的な距離が、心の距離を生んでしまうことがあるのです。
このように、実家の問題は「突然始まること」と「負担の偏り」という構造から、どんなご家庭にとっても難しいテーマになり得ます。では、もしこのテーマから目をそらし、先延ばしにしてしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。次章では、放置が招く「3つの静かなリスク」について見ていきましょう。
先延ばしが招く、3つの静かなリスク
「とりあえず、現状維持で…」その判断は、一見すると平穏を保つ選択のように思えるかもしれません。しかし、時間の経過と共に、いくつかのリスクが静かに、しかし着実に膨らんでいきます。ここでは「お金」「家の価値」「家族の心」という3つの側面から、そのリスクを解説します。
リスク①【お金】固定資産税の負担が重くなる可能性
通常、住宅が建っている土地には固定資産税の優遇措置があります。しかし、管理が行き届かず、周辺環境への影響が懸念される状態になると、自治体から「特定空家(とくていあきや)」に指定されることがあります。その場合、この優遇措置が適用されなくなり、土地の固定資産税の負担がこれまでより重くなる可能性があります。この重要な制度について、空き家所有者の5割以上が「知らない」と回答しているのが現状です【出典:1】。意図せず負担が増えてしまう前に、正しい知識を持つことが大切です。
リスク②【家の価値】管理の頻度が、資産価値を左右する
家の価値は、何もしなければ少しずつ下がっていきます。そのスピードを左右するのが、管理の質です。調査によると、管理の頻度が「年に1〜数回」の家は「月に1〜数回」の家よりも、「構造上の不具合が生じている」割合が高いというデータがあります【出典:1】。この点は国の別の調査でも裏付けられており、住宅の維持管理について「特に何もしていない」と答える世帯も一定数存在するなど、管理への意識の差が家の状態に直結していることがうかがえます【出典:2】。「たまに帰って掃除しているから」というだけでは、雨漏りや目に見えない部分の劣化は防ぎきれないかもしれません。
リスク③【家族の心】「家財の整理」という大きな壁
空き家の処分を考える際、多くの方が精神的なハードルとして挙げるのが「家財の整理」です。実際に、37.4%の方がこれを課題だと感じています【出典:1】。親御様の人生が詰まった品々を一つひとつ整理していくのは、時間も、そして心のエネルギーも使う大変な作業です。誰が、いつ、どのように費用をかけて片付けるのか。この重いテーマを前にすると、ご兄弟の間でも会話が止まってしまいがちです。思い出の品々と向き合う時間は、お金以上にデリケートな問題と言えるでしょう。
税金、家の価値、そして家族の心。問題を先延ばしにすることは、これらの大切なものを少しずつすり減らしてしまう可能性があります。この現実を踏まえ、次章では、ご兄弟が心を一つにして円満に解決するための具体的な「3つのステップ」をご紹介します。
兄弟で円満に実家を整理する「相続3ステップ」
複雑に思える実家の問題も、正しい手順で丁寧に進めれば、きっと良い解決策が見つかります。感情的なすれ違いを避け、ご兄弟全員が納得して前に進むための秘訣は、「①客観的な事実で土台を作り、②全員の想いをテーブルに乗せ、③公平な第三者と歩む」ことです。
【Step 1:現状把握】まずは全員で「実家のカルテ」を作る
最初のステップは、ご実家の現状を誰もが客観的に理解できるよう、一枚の「カルテ」にまとめることです。感情的な議論になる前に、まず以下の情報を事実としてご兄弟全員で共有しましょう。
- 資産価値: 不動産会社数社に簡易査定を依頼し、現在の市場価値を知る。
- 維持費: 固定資産税の納税通知書や光熱費などをリストアップし、年間でいくらかかっているか把握する。
- 家の状態: 雨漏り箇所や庭の状態など、気になる部分を写真に撮って共有する。
- 課題: 残っている荷物の量、駐車場の有無など、今後の活用を考える上での懸念点を洗い出す。
この「カルテ」が、建設的な話し合いを進めるための、ぶれない土台となります。
【Step 2:意思表示】それぞれの「想い」をテーブルに乗せる
現状を共有できたら、次にそれぞれの希望や想いを話し合います。主な選択肢は以下の4つです。それぞれのメリット・デメリットを表にまとめ、冷静に比較検討することが大切です。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却する | 維持管理の負担から解放される。現金を公平に分割しやすい。 | 思い出の詰まった家がなくなる寂しさ。売却に時間がかかることも。 |
| 賃貸する | 定期的な収入源になる可能性がある。家を残せる。 | リフォーム費用や管理費用がかかる。空室のリスク。 |
| 誰かが住む | 家が活用され、管理の心配が減る。 | 住む人の費用負担や、他の兄弟への配慮で合意形成が難しい場合も。 |
| 更地にする | 管理が楽になる。土地として活用しやすくなることも。 | 多額の解体費用がかかる。固定資産税の優遇がなくなる。 |
これらの選択肢を比較検討する上で、やはり気になるのが具体的な「費用」でしょう。解体費用やリフォーム、売却時にかかる税金など、空き家相続にまつわるお金の話をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【Step 3:専門家相談】第三者の視点で「納得のいく道筋」を探す
ご兄弟だけの話し合いでは、知識の差や過去の経緯から、どうしても議論が平行線になってしまうことがあります。そんな時こそ、相続に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。専門家は、単に手続きの代行をするだけではありません。
- 各選択肢を選んだ場合の税金シミュレーションを行い、金銭的な見通しを客観的に示します。
- 金銭的な公平さだけでなく、これまでのご家族の貢献度といった感情的な側面にも配慮しながら、皆様が納得できる分割案を一緒に考えます。
- 複雑な議論の「交通整理役」として、ご家族の話し合いが円滑に進むようサポートします。
利害関係のない第三者が加わることで、安心して本音を話し合え、ご家族全員にとって最善の道筋を見つけやすくなります。
まずはお気軽にご相談ください
「自分たちだけで話し合うのは、少し難しそうだ…」と感じたら、それは専門家に相談するタイミングです。名古屋相続税無料診断センターでは、相続専門の税理士が、ご家族ごとの状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えます。初回のご相談は無料です。
お急ぎの方は 0120-339-719 からご予約ください。
(受付時間 平日9:00〜18:00)
よくあるご質問
親がまだ元気なうちに、相続や空き家の話をするのは気が引けます。どう切り出せばいいですか?
「終活」や「実家の片付け」といった、よりソフトな話題から入るのがおすすめです。「この前テレビで見たんだけど、将来のために一度、家のことを整理しておくと安心みたいだよ」といった形で、ご両親を主役にし、あくまで「将来のための前向きな準備」として提案してみてはいかがでしょうか。親御様の想いを尊重しながら、家族みんなで考えるきっかけを作ることが大切です。
もし、兄弟間で意見がまとまらなかった場合はどうすればよいですか?
まずは、なぜ意見が違うのか、それぞれの考えの背景にある想いや懸念(例えば「費用負担が心配」「思い出を手放したくない」など)を、時間をかけてじっくり聞くことが重要です。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停という方法もありますが、その前に専門家を交えて話し合うことを強くお勧めします。第三者が入ることで、感情的な対立を避け、客観的な情報に基づいた公平な解決策を見つけやすくなります。
専門家に相談すると、費用が高そうで心配です。
ご心配はもっともです。だからこそ、多くの専門家事務所では「初回無料相談」を設けています。名古屋相続税無料診断センターでも、まずは無料相談でお客様の状況をじっくりお伺いし、どのようなサポートが可能か、費用はどのくらいかかりそうかを丁寧にご説明します。その上でご判断いただけますので、安心して「まず話を聞いてみる」という気持ちでご活用ください。
参考文献
- 国土交通省住宅局 (令和7年8月). 令和6年空き家所有者実態調査結果. https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000233.html
- 国土交通省 (令和7年8月29日). 報道発表資料:住宅の維持管理の実態などを新たに調査しました!~令和5年住生活総合調査の調査結果(確報)~. https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000232.html
免責事項
本記事に掲載された情報は、一般的な情報提供を目的とするものであり、特定の個別の事案に対する税務上・法律上のアドバイスではありません。具体的な税務上の判断や手続きについては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。本記事の情報に基づいて行われた行為により生じたいかなる損害についても、当センターは一切の責任を負いません。
本記事は、AIを高度なリサーチおよび執筆のアシスタントとして活用し、作成されました。記事の内容については、監修者である税理士が全ての正確性を確認し、最終的な責任を負っています。
著者情報
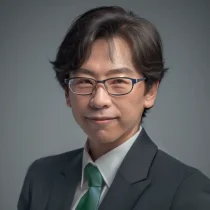
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
最新の投稿
コラムの最新記事
- 【2026税制改正】賃貸不動産・小口化商品の相続税評価見直し|5年ルールの影響と対策
- 相続した実家、片付ける前に「やってはいけないこと」だけ先に確認――3か月・相続放棄・法定単純承認の地雷を避ける
- 相続税の税務調査は「実地調査」だけじゃない?増える“電話・手紙”と、無申告への厳しい視線【令和6事務年度】
- 引っ越しだけじゃない ペンリィが変えるかもしれない「死亡・相続手続き」のこれから
- 見つからない不動産"を防ぐには?2026年開始の新制度「所有不動産記録証明制度」の賢い使い方と知っておべき限界
- 『配偶者に全部』は本当に安心? 名古屋で考える二次相続モデルケースと対応策
- 「私の場合は使える?」名古屋市の空き家3000万円控除、対象か3分で診断【税理士監修】