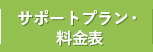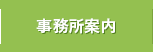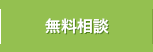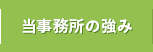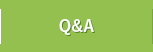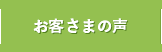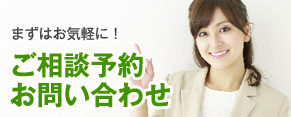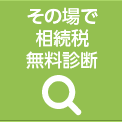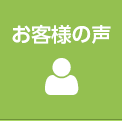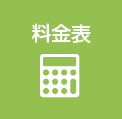【相続税】専門税理士がむずかしい言葉を分かりやすく説明する件

こんにちは、名古屋相続税無料診断センターの佐治です。
相続が起こって亡くなった人の財産を相続すると「もしかしたら相続税がかかるかも!?」って、心配になる人が多いです。
そもそも相続税ってどんなときにかかるのか
相続税がかかる人ってどんな人なのか
この記事では相続税専門の税理士が、
相続税と相続税がかかる財産について分かりやしく説明します。
|
もくじ
|
1.そもそも相続税って?
相続の話はいろんなところで耳にしますよね。「相続税ってなにって?」て聞かれると「相続が起こっ
たらかかる税金だよ!」って当たり前ですが、もう少し詳しく言うと、相続や遺贈(遺言で財産ももら
うこと)で取得した財産及び相続時精算課税っていう特別な贈与を使って取得した財産の合計額が基礎
控除を超えると、超えた部分に対して相続税がかかります。相続税がかかかる場合、相続税の申告と納
税が必要になり、その期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
2.相続税の基礎控除と正味の財産額
相続税の基礎控除っていうのは、「亡くなった人が持っていた財産のうち一定の金額までなら相続税は
かかりませんよ!」という最低限度のことです。
相続税の基礎控除は次のように計算します。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
遺産の総額が基礎控除を超えると相続税の申告を行う必要があり、
遺産相続が基礎控除以下に収まれば、相続税の申告は必要ありません。
ここで、「法定相続人」って言葉が出てきました。簡単にいうと相続人の数って考えておけばOKで
す。
ちょっとややこしいのが、「相続人の数」の中には、相続放棄をした人がいたとしてもその放棄をした
人も含めます。普通相続放棄をすると、別に人が新たに相続人になるのですが、「法定相続人」を計算
するときは相続放棄をして新しく相続人になった人は人数に含めないのです。
もうひとつ、亡くなった人に養子がいるときは、養子の人数を1人または2人まで追加してもいいとい
うルールがあります。これは別のところで説明します。
相続税の基礎控除は2014年までは
「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の人数」
だったのですが、2015年から
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」
へ変更されました。
正味の遺産額というのは、亡くなった人の財産のうち、相続税法で決められている非課税財産、葬式費
用、その他の債務を控除し、相続が始まる3年前までにあった贈与財産を加算して計算します。
そして正味の財産額が基礎控除額を超えると相続税がかかりますので、相続税の申告と納税が必要にな
ります。
3.相続税がかかる人と相続税がかかる財産
相続税がかかる人はいくつか条件があります。
1) 相続や遺贈によって財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がある人(その
人が一時的に日本に住所があるような場合は、亡くなった人が一時的に日本に住んでいたとか、亡くな
った人が日本に住んでいなかった場合を除きます。)
⇒もらった財産のすべてが課税される財産です
2)相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がなく次に当てはまる人
⇒もらった財産のすべてが課税される財産です
イ 財産をもらったときに日本国籍をがある人は、次のいずれか
(イ) 相続が起こる前の10年以内に日本に住所がある人
(ロ) 相続が起こる前の10年以内に日本に住所がない人(亡くなった人が一時的に日本に住んでいたと
か、亡くなった人が日本に住んでいなかった場合を除きます。)
ロ 財産をもらったときに日本国籍がない人(亡くなった人が一時的に日本に住んでいたとか、亡くな
った人が日本に住んでいなかった場合を除きます。)
3) 相続や遺贈で日本国内にある財産もらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がある人
(1)に該当する人を除きます。)
⇒日本国内にある財産に課税されます
4) 相続や遺贈で日本国内にある財産ををもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所がな
い人(2)に該当する人を除きます。)
⇒日本国内にある財産に課税されます
5) 上記1)~4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税という特殊な贈与で財産
をもらった人
⇒相続税精算課税でもらった財産に課税されます
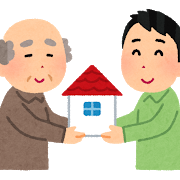
4.まとめ
相続が起こってもらった財産が基礎控除を超えた部分について相続税がかかります。そして相続税がか
かる財産は亡くなった人や相続財産をもらった人が日本に住所があったかなかったかで課税される財産
の範囲が変わってきます。
この点だけはぜひ覚えておいてください。
もし相続税申告が必要にも関わらず、申告しない場合にはリスクがあるので、心配な人は、相続税専門
の税理士へ相談することをおすすめします。
著者情報
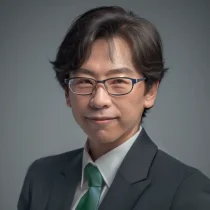
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
コラムの最新記事
- 【2026税制改正】賃貸不動産・小口化商品の相続税評価見直し|5年ルールの影響と対策
- 相続した実家、片付ける前に「やってはいけないこと」だけ先に確認――3か月・相続放棄・法定単純承認の地雷を避ける
- 「スマホで遺言」はどこまで本当?厳格化の理由と、争いの論点が変わる未来
- 相続税の税務調査は「実地調査」だけじゃない?増える“電話・手紙”と、無申告への厳しい視線【令和6事務年度】
- 引っ越しだけじゃない ペンリィが変えるかもしれない「死亡・相続手続き」のこれから
- 見つからない不動産"を防ぐには?2026年開始の新制度「所有不動産記録証明制度」の賢い使い方と知っておべき限界
- 『配偶者に全部』は本当に安心? 名古屋で考える二次相続モデルケースと対応策