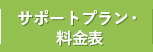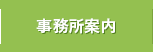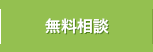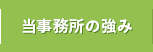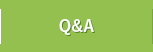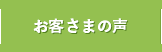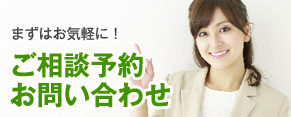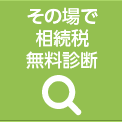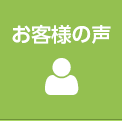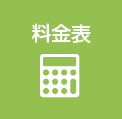見つからない不動産”を防ぐには?2026年開始の新制度「所有不動産記録証明制度」の賢い使い方と知っておべき限界
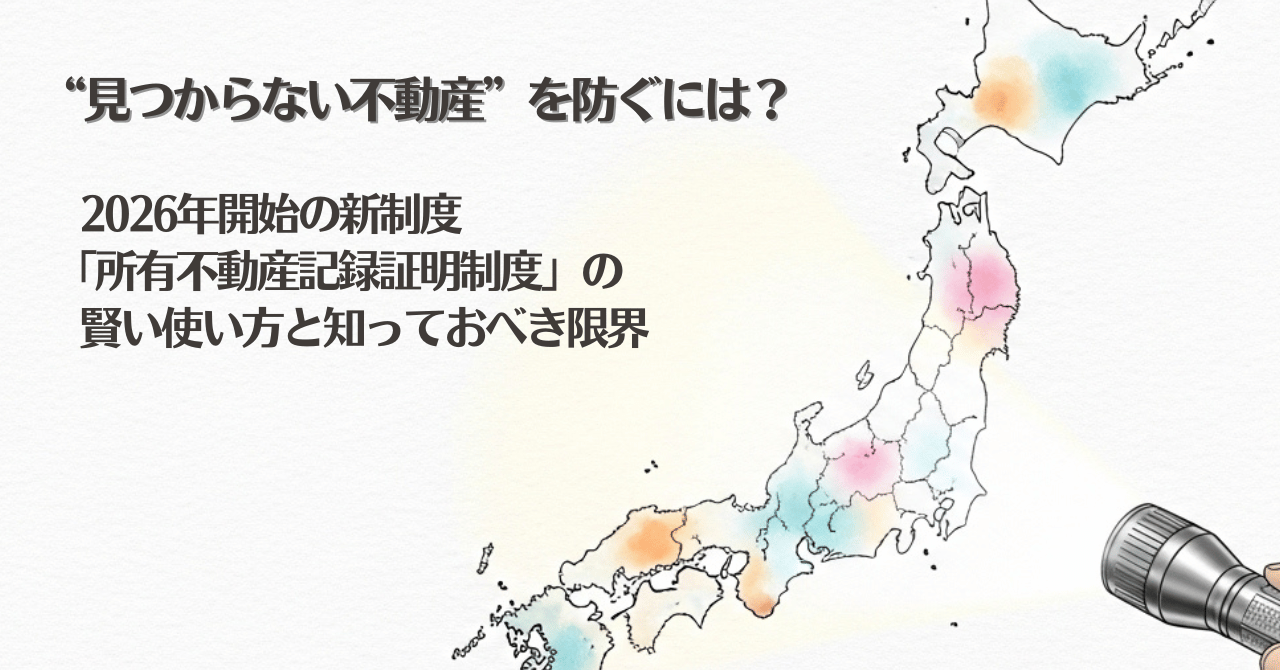
これまで数多くの相続相談に対応してきた税理士・宅地建物取引士の佐治英樹が解説します。「親の不動産がどこにあるか全部わからない」という不安は、相続の準備段階で多くの方が抱える深刻な悩みです。その解決の切り札として期待される新制度が始まりますが、その賢い使い方を知らなければ、かえって将来のリスクを見逃すことにもなりかねません。
この記事では、
1. 相続準備の“新常識”となる制度の基本
2. なぜそれだけでは不十分なのかという構造的な理由
3. 私たちが今からできる、3つの具体的なステップ
の3点を、専門用語を避けて分かりやすくお伝えします。
はじめに:親の不動産、すべて把握できていますか?相続準備の“新常識”
「実家以外にも、どこかに土地を持っていると聞いたことがある」「父が亡くなった後、全く知らない土地の納税通知書が届いて驚いた」…。このような話は、決して珍しいことではありません。いざ相続という場面になって、亡くなった親が所有していた不動産の全容がわからず、手続きが難航するケースは後を絶ちません。最悪の場合、財産を見つけられないまま相続税の申告期限を過ぎてしまったり、後から不動産が見つかって遺産分割協議をやり直したりする事態も起こり得ます。
こうした問題を解決する強力な味方として、2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度(仮称)」がスタートします。これは、相続準備のあり方を大きく変える可能性を秘めた、まさに“新常識”ともいえる制度です。しかし、どんな便利な道具も、その特性と限界を知らなければ宝の持ち腐れになってしまいます。この記事では、あなたがこの新制度を賢く使いこなし、将来の不安を安心に変えるための知識と具体的な行動を解説していきます。
この章では、相続準備における不動産把握の重要性と、その解決策として新制度が登場する背景を説明しました。次章では、その「所有不動産記録証明制度(仮称)」とは一体何なのか、基本のキから見ていきましょう。
第1章:そもそも「所有不動産記録証明制度(仮称)」とは?3分でわかる基本のキ
では、私たちの相続準備をどう変えるのか。この制度の最も重要なポイントは、「特定の人物(名義人)の氏名と住所をもとに、その人が日本全国に所有している不動産を、法務局が一覧にして証明してくれる」という点にあります。これまで、ある人がどこに不動産を持っているかを調べるには、市区町村ごとに「名寄帳(なよせちょう)」を取り寄せたり、固定資産税の納税通知書を確認したりする必要がありました。しかし、これらの方法では、他の市区町村にある不動産や、税金のかからない私道などを見つけることは困難でした。
| 調査方法 | 調査範囲 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 名寄帳 | 市区町村ごと | その自治体内の資産を一覧できる | 他の自治体の資産はわからない |
| 納税通知書 | 自治体ごと | 手元にあればすぐに確認できる | 非課税の不動産は載っていない |
| 新制度 | 全国一括 | 一度の手続きで全国の不動産を網羅 | 登記情報が古いと漏れる可能性 |
この新制度を使えば、相続人が法務局で一度手続きをするだけで、亡くなった親(被相続人)が登記している不動産を原則としてすべてリストアップできます。これにより、財産調査にかかる時間と手間が劇的に削減され、不動産の“見落とし”という最大のリスクを大幅に減らすことができるのです。ただし、そもそも登記されていない建物などは対象外となる点には注意が必要です。それでも、多くのケースで相続手続きにおける革命的なツールといえるでしょう。
この章では、所有不動産記録証明制度の画期的な仕組みを解説しました。しかし、この便利な制度にも弱点があります。次章では、なぜこの制度が“万全”ではないのか、その構造的な限界に迫ります。
第2章:なぜ“万全”ではない?制度が抱える3つの構造的限界
全国の不動産を一覧化できると聞くと、「これで万全だ」と感じるかもしれません。しかし、この制度には、知っておかなければならない構造的な限界、つまり弱点が存在します。その理由は大きく分けて3つあり、これらが“見つからない不動産”が残ってしまう可能性を生んでいます。
第一に、「情報の“古さ”の問題」です。この制度は、法務局の登記データベースに登録されている「氏名」と「住所」をもとに検索を行う仕組みです。もし、親が若い頃に買った不動産の登記住所が、引っ越し前の古い住所のまま更新されていなかったらどうなるでしょうか。現在の住所で検索をかけても、その古い不動産はヒットせず、一覧から漏れてしまうリスクがあります。2026年4月からは住所変更登記も義務化されますが、それ以前に更新が止まっている不動産は、日本中に数多く存在すると考えられています。
第二に、「土地の“境界”の問題」です。日本の土地データは、その土台となる地図の精度が場所によってバラバラだという課題を抱えています。国土交通省の発表(令和5年度末時点)によると、土地の境界や面積を正確にする地籍調査(ちせきちょうさ)の進捗率は、全国で約54%に留まっています。もちろん、都市部や災害リスクの高い地域などの「優先実施地域」では進捗率が約81%に達しており、重要な場所から整備が進められています。しかし、それでもなお日本の土地のおよそ半分は、明治時代の古い地図を基にした、境界が曖昧なデータのままなのです。これにより、証明書に記載はあっても、その土地が具体的にどこを指すのか判然としない、というケースも起こり得ます。
第三に、「手続き上の“壁”の問題」です。この証明書は誰でも取得できるわけではなく、本人や相続人など、法律で定められた関係者しか請求できません。また、請求には数百円から千円程度の手数料が必要になると想定されています。これはプライバシー保護の観点からは当然の措置ですが、制度の存在を知らなければ、そもそも活用するという発想に至らない可能性があります。便利な道具も、その存在と使い方を知らなければ意味がないのです。
この章では、制度が万能ではない3つの理由を解説しました。これを踏まえ、次章では、私たちが具体的に何をすべきなのか、本当に大切な3つのステップについてお話しします。
第3章:では、どうすれば?今日からできる、未来を変える3つの小さなステップ
制度の限界を知り、不安を感じられたかもしれません。しかし、ご安心ください。将来のリスクは、今からできる3つの具体的なステップで十分に減らすことができます。大切なのは、ご両親が元気で、冷静に話ができる「今」だからこそ、行動を起こすことです。
ステップ1:まず、固定資産税の「納税通知書」を探してみる
役所に行く必要も、難しい書類を取り寄せる必要もありません。まずやるべきことは、ご家庭にある「固定資産税の納税通知書」を探して、見てみることです。これは毎年4月~6月頃に市区町村から不動産の所有者に送られてくる書類で、通常、ファイルなどにまとめて保管されていることが多いはずです。この通知書には、その市区町村内で課税対象となっている不動産の一覧が記載されています。これ以上に確実で、手間も費用もかからない現状把握の方法はありません。これこそが、誰でも今日から始められる、最も現実的な「最初のステップ」です。
ステップ2:未来の「うっかり忘れ」を防ぐ、ひと手間を習慣にする
これは、未来の家族のために、私たち自身ができるとても簡単なことです。不動産をお持ちの方が引っ越しや結婚で住所・氏名が変わった際の「登記情報も更新する」という意識を持つことです。2026年4月からは、この変更登記が2年以内に義務化されます。しかし、これを「面倒な義務」と捉えるのではなく、「免許証の住所変更と同じ、当たり前の手続き」と考えてみてください。この小さなひと手間が、将来あなたの大切な家族が、不動産を探し回る苦労をせずに済むための、最高のプレゼントになるのです。
ステップ3:家族と話す「気まずさ」を乗り越える、小さなきっかけ作り
これが最も重要で、そして多くの人が最も難しいと感じることかもしれません。親が元気なうちに、財産の話をするのは気まずいものです。「気まずい空気になったらどうしよう」「怒らせてしまうかもしれない」。そう感じてしまうのは、ごく自然なことです。だからこそ、ステップ1で見つけた「納税通知書」をきっかけに会話を始めてみるのはいかがでしょうか。
会話を切り出す、やさしいヒント
「そういえば、ニュースで見たんだけど、2026年から不動産の新しい制度が始まるらしいよ。この納税通知書に載っている不動産の登記住所って、今の住所のままになっているかな?念のため、気になって」
重要なのは、詮索ではなく「心配している」という気持ちを伝えることです。「将来、私たちが手続きで困らないように」という思いやりが伝われば、きっとご両親も話を聞いてくれるはずです。この小さな勇気が、未来の家族を大きなトラブルから守るのです。
まとめ:新制度を賢く活用し、安心な未来を準備しよう
この記事では、2026年2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度(仮称)」の賢い使い方と、知っておくべき限界について解説してきました。この制度は、相続準備における不動産調査の負担を劇的に軽くする、非常に強力なツールであることは間違いありません。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、制度が参照する登記情報そのものが正確であることが不可欠です。
情報の“古さ”や土地の“境界”といった構造的な限界がある以上、私たちは制度を過信せず、「自ら情報を最新に保ち、家族で共有する」という意識を持つことが何よりも重要になります。本日ご紹介した3つの具体的なステップは、そのための第一歩です。この新制度を、単に「便利な証明書」としてだけでなく、「家族の財産と未来について考える良いきっかけ」として捉え、賢く活用していきましょう。
よくあるご質問
私は賃貸住まいで不動産を持っていませんが、この記事の内容は関係ありますか?
はい、大いに関係があります。ご自身が不動産を持っていなくても、ご両親が所有している場合、将来あなたが相続人になる可能性があります。その際、ご両親の不動産の登記情報が古いままだと、この記事で解説したような“見つからない不動産”のリスクに直面するのは、あなた自身です。ぜひ、この制度の話をきっかけに、ご実家の状況についてご両親と話す機会を持ってみてください。
請求の際、本人確認書類の他に何が必要になりますか?
もしご自身が相続人として、亡くなった親の不動産を調べる場合は、ご自身が相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要になります。どのような書類が必要になるかの詳細は、今後法務省から公表される情報を確認したり、お近くの法務局に問い合わせたりすることをお勧めします。
結局、証明書の取得や登記の変更には、いくらくらい費用がかかるのでしょうか?
所有不動産記録証明書の発行手数料は、まだ正式に公表されていませんが、あくまで目安として数百円から千円程度と想定されています。住所変更登記をご自身で行う場合、登録免許税として不動産1つにつき1,000円かかります。司法書士に依頼する場合は、これに加えて1〜2万円程度の報酬が一般的ですが、これは案件の難易度などによって変動します。
この記事を読んで、ご自身の状況に少しでも不安を感じたり、具体的な準備について相談したいと思われたりしたかもしれません。家族の財産を守るための第一歩は、現状を正しく知ることから始まります。もし具体的なご不安があれば、私たち専門家がいつでもお力になりますので、お気軽にご相談ください。
参考文献
- 法務省:「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」 – https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00499.html#mokuji1
- 法務省:相続登記の申請義務化について 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行) – https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji10
- 国土交通省:「土地の戸籍」に関する最新の調査実施状況を公表します – https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo06_hh_000001_00015.html
免責事項
本記事に掲載された情報は、2025年9月16日時点の一般的な情報提供を目的とするものであり、特定の個別の事案に対する税務上・法律上のアドバイスではありません。具体的な税務上の判断や手続きについては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。本記事の情報に基づいて行われた行為により生じたいかなる損害についても、当センターは一切の責任を負いません。
本記事は、AIを高度なリサーチおよび執筆のアシスタントとして活用し、作成されました。記事の内容については、監修者である税理士が全ての正確性を確認し、最終的な責任を負っています。
著者情報
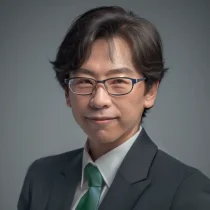
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
コラムの最新記事
- 相続税の税務調査は「実地調査」だけじゃない?増える“電話・手紙”と、無申告への厳しい視線【令和6事務年度】
- 引っ越しだけじゃない ペンリィが変えるかもしれない「死亡・相続手続き」のこれから
- 『配偶者に全部』は本当に安心? 名古屋で考える二次相続モデルケースと対応策
- 兄弟で揉めない「実家の空き家」相続ガイド|後悔しないための3つのステップ
- 「私の場合は使える?」名古屋市の空き家3000万円控除、対象か3分で診断【税理士監修】
- 【名古屋市版】空き家相続の放置コストを1分で簡単シミュレーション!税金が6倍になる『特定空家』指定前に税理士が教える3つの対策
- 【パーソナライズ相続手続きナビゲーター】あなただけの相続スケジュールを自動作成