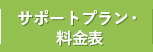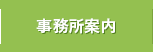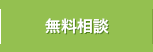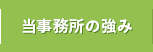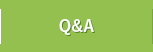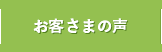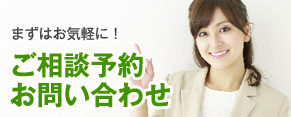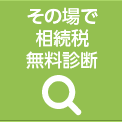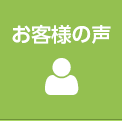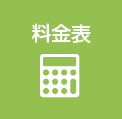『配偶者に全部』は本当に安心? 名古屋で考える二次相続モデルケースと対応策
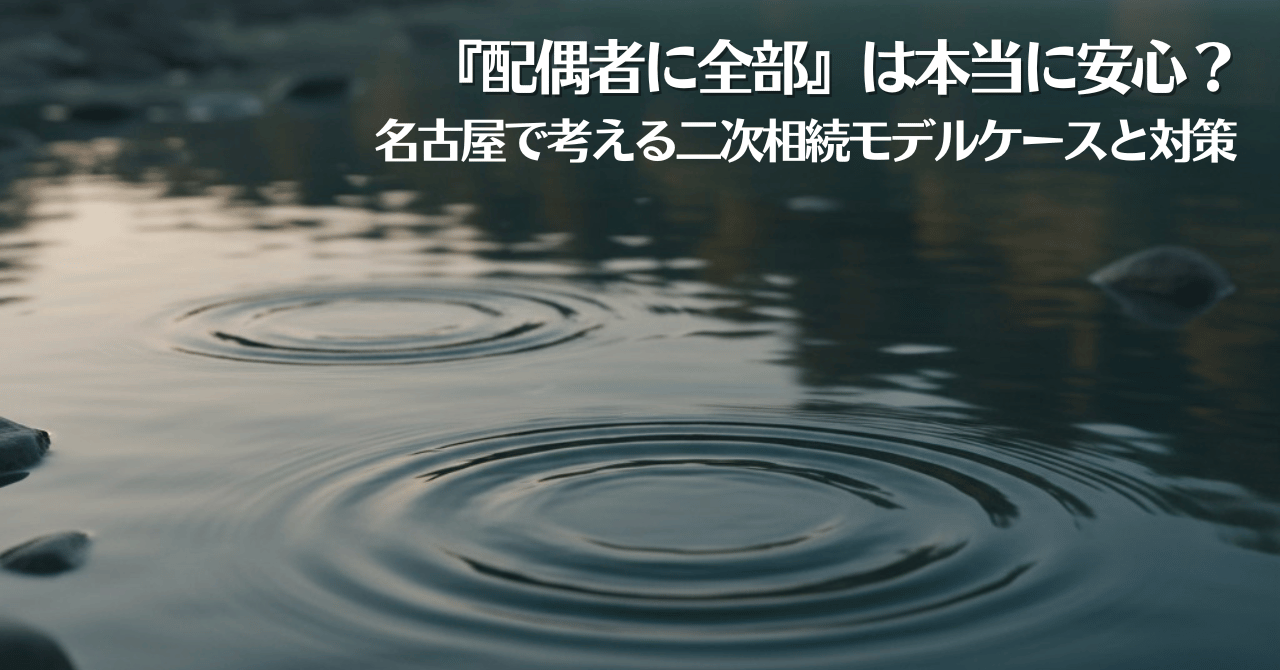
「夫が亡くなったら、財産はすべて妻である私が相続すれば安心」
「子どもたちに迷惑はかけたくないから、まずは配偶者へ」
相続を考え始めたとき、多くの方がこのように思われるのではないでしょうか。確かに、最初の相続(1次相続)では、税金がゼロになるケースも少なくありません。
もちろん、大切なご家族を亡くされた直後に「次」のお話をすることは、お辛いことと存じます。そのお気持ちは、何よりも尊重されるべきです。
しかし、少しだけ心が落ち着かれたタイミングで、この「2回目の相続」について考えることは、残されたご家族が将来困らないようにするための、未来への「思いやり」や「愛情」の形とも言えるのです。
この記事では、相続の専門家が、
- なぜ2次相続で税負担が重くなるのか?
- ご家族の誰もが不幸にならないための具体的な対策
- 「2回合計で見て」ご家族の負担を最小化する考え方
を、ゼロから丁寧に解説します。これは単なる節税の話ではありません。ご家族の未来の安心を、みんなで一緒に作るためのガイドブックです。
なぜ?「2回目」の相続で税金が急に重くなる3つの理由
1次相続では税金がかからなかったのに、なぜ2次相続では高額な税金が発生するのでしょうか。それには、主に3つの“制度の切れ目”が関係しています。
理由1:最強の切り札「配偶者の税額軽減」が使えない
1次相続で税負担を大きく減らせる最大の理由が、この「配偶者の税額軽減」です。これは、配偶者が相続した財産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い金額まで相続税がかからないという強力な制度です。
しかし、2次相続(例:母が亡くなり、子が相続)では、相続人は「子」だけ。当然、この制度は使えません。財産がそのまま課税対象になってしまいます。
理由2:税金の基礎控除額が「縮小」してしまう
相続税には、誰でも使える「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。この金額を超えた部分にだけ、相続税がかかります。
- 1次相続(父が死亡): 法定相続人は母・子2人の計3人 → 基礎控除4,800万円
- 2次相続(母が死亡): 法定相続人は子2人の計2人 → 基礎控除4,200万円
法定相続人が1人減るだけで、課税対象となる金額が600万円も増えてしまうのです。
理由3:資産(特に不動産)の価値が上がってしまうリスク
1次相続から2次相続までの間には、数年〜十数年の時間が経過します。その間に、相続した不動産の価値や株価が上昇した場合、その値上がり分も2次相続の課税対象に加算されます。特に地価が上昇傾向にあるエリアでは、このリスクは無視できません。
【効果は611万円!】やりがちな選択 vs 最適な選択(税額比較)
当センターの既存解説と同じ条件(財産2億円/妻+子2人)で、一次相続と二次相続を通じた「合計税額」を比較します。
【対策なし】多くの方が選びがちな「配偶者控除の最大活用」
一次相続:妻1億6,000万円、子2人が各2,000万円
二次相続:妻の遺産1億6,000万円を子2人で各8,000万円
一次+二次の合計相続税額
合計 2,680万円
【対策あり】二次相続まで考えた「最適な分割」
一次相続:妻6,600万円、子2人が各6,700万円
二次相続:妻の遺産6,600万円を子2人で各3,300万円
一次+二次の合計相続税額
合計 2,069万円
このように、多くの方が選びがちな方法と、二次相続まで見据えた最適な分割を比較するだけで、将来の合計税額に611万円もの差が生まれる可能性があるのです。
より詳しいシミュレーションと背景解説は、こちらの解説ページをご覧ください。
※上記は特定モデルケースでの計算例です。実際の税額はご家庭の条件により大きく異なります。
ご家庭でできる具体的な対策4選
2回合計での負担を減らすには、1次相続の時点での「遺産の分け方」が鍵となります。ただし、これらの方法は強力な一方、使い方を間違えると「不動産が売れない」「家族の関係がこじれる」といった新たな問題を生むこともあります。専門家と相談しながら、ご家庭に合った最適な方法を選ぶことが重要です。
-
子のための資金も、バランス良く確保する
お母様の生活資金を最優先で確保した上で、余裕がある部分から、子の世代へ計画的に財産を分けておく方法です。
-
「小規模宅地等の特例」を“最適な人”が使う
ご自宅の土地の評価額を最大80%減額できる特例です。誰が使うのが「2回合計で」最も有利になるか、シミュレーションが欠かせません。
-
「配偶者居住権」で“所有”と“住む”を分ける
お母様は亡くなるまで安心して住み続けられ、所有権は子が持つ、という方法です。これにより2次相続の対象財産を減らせます。安易な共有名義と違い、将来のトラブルを避けやすいという利点もあります。
-
資産の性質で見極める
将来値上がりしそうな資産は早めに子へ、当面の生活資金である預貯金は配偶者へ、という考え方です。ただし、ご自宅しか財産がない、というケースも少なくありません。その場合は無理に分けるのではなく、別の方法を検討します。
【地価データで見る】名古屋特有の注意点とリスク
一般論だけでなく、私たちが拠点を置く「名古屋」の状況を踏まえることが大切です。
国土交通省が発表した地価公示によると、名古屋圏の住宅地は4年連続で地価が上昇しています。
令和7年地価公示では、名古屋圏の住宅地は、対前年平均変動率が+2.3%と、4年連続の上昇となった。上昇幅は前年の+2.5%からやや縮小したものの、都心部へのアクセスに優れた地域や生活利便性の高い地域を中心に、依然として堅調な地価上昇が継続している。
このデータが示すのは、「何もしなければ、将来の相続税評価額は上がっていく可能性が高い」という事実です。
特に名古屋市内の中心部や生活利便性の高いエリアに不動産をお持ちの場合、1次相続から2次相続までの間に評価額が数百万〜数千万円上昇することも考えられます。その値上がり分が、将来お子さんたちの税負担に直結するのです。
まとめ:家族の未来を守るための「対話のきっかけ」に
この記事でお伝えしたかった最も大切なことは、『相続は、税金の計算式だけで決めるのではなく、家族の未来の物語として考える』という視点です。
「配偶者に全部」という選択は、一見、愛情深い選択に見えるかもしれません。しかし、それがかえって将来のお子さんたちを苦しめる可能性があるのなら、一度立ち止まって考える必要があります。
この記事を読んで、「我が家の場合は、どう分けるのが一番良いんだろう?」「そもそも、誰が何を相続したいと思っているんだろう?」そう思われたなら、ぜひこの記事をご家族が集まる際の話の「たたき台」として使ってみてください。専門家が書いた客観的な情報としてテーブルに置くことで、お金の話がしやすくなるかもしれません。
そして、ご家族だけでは答えが出ない時、私たち専門家がいます。私たちは、ただ税金を計算するだけではありません。ご家族一人ひとりのお気持ちを伺い、全員が納得できる円満な分割案を一緒に考え、その上で最も有利な税金の申告を行うのが仕事です。
最初の相談は無料です。
ご家族の未来の安心を設計する、その第一歩を今日、踏み出してみませんか。
「自分たちだけで話し合うのは、少し難しそうだ…」と感じたら、それは専門家に相談するタイミングです。名古屋相続税無料診断センターでは、相続専門の税理士が、ご家族ごとの状況に合わせた最適な解決策を一緒に考えます。初回のご相談は無料です。
お急ぎの方は 0120-339-719 までご連絡ください。
(受付時間 平日9:00〜19:00 土日夜間対応)
本記事の注意事項
この記事は2025年9月1日時点の法令に基づき作成されています。相続税に関する法改正は頻繁に行われますので、最新の情報は国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、専門家にご相談ください。また、記事内で示された税額は特定の条件下でのシミュレーションであり、個別の案件における税額を保証するものではありません。
この記事は、人間による監督の下でAI(人工知能)を活用して生成されました。内容は、公開されている情報源に基づき、税理士・行政書士の監修を受けています。
著者情報
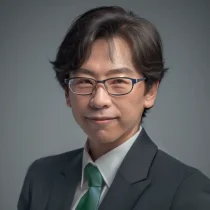
- 税理士(名古屋税理士会 登録番号_113665), 行政書士(愛知県行政書士会 登録番号_11191178), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
最新の投稿
コラムの最新記事
- 【2026税制改正】賃貸不動産・小口化商品の相続税評価見直し|5年ルールの影響と対策
- 相続した実家、片付ける前に「やってはいけないこと」だけ先に確認――3か月・相続放棄・法定単純承認の地雷を避ける
- 相続税の税務調査は「実地調査」だけじゃない?増える“電話・手紙”と、無申告への厳しい視線【令和6事務年度】
- 引っ越しだけじゃない ペンリィが変えるかもしれない「死亡・相続手続き」のこれから
- 見つからない不動産"を防ぐには?2026年開始の新制度「所有不動産記録証明制度」の賢い使い方と知っておべき限界
- 兄弟で揉めない「実家の空き家」相続ガイド|後悔しないための3つのステップ
- 「私の場合は使える?」名古屋市の空き家3000万円控除、対象か3分で診断【税理士監修】